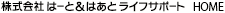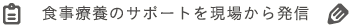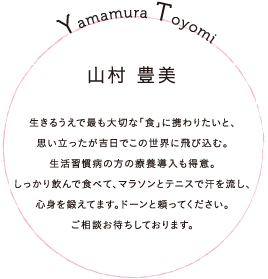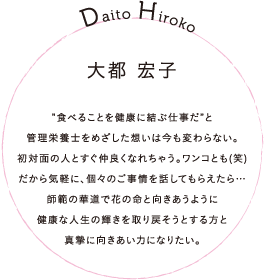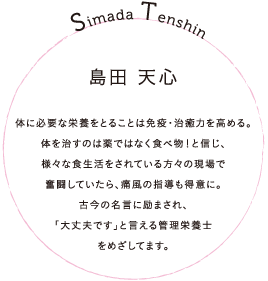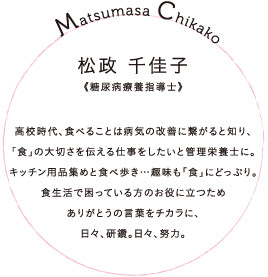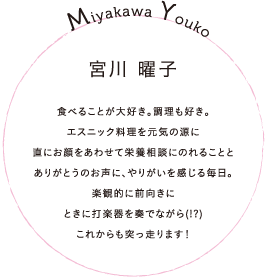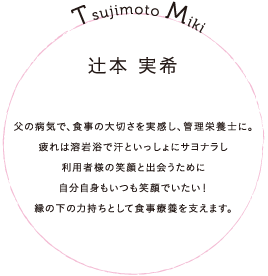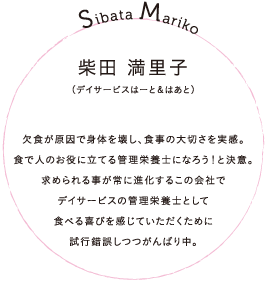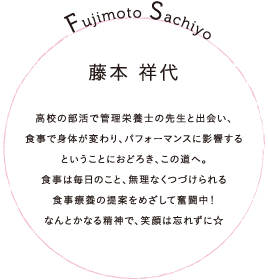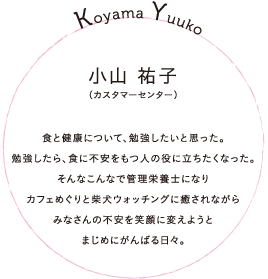こんにちは。めでぃ北摂の島田です。
気がつけば早5月も終わり、深緑の6月になる季節。
暑くなったり、寒くなったりほんとに体調管理が難しく
ご高齢の利用者さまの体調も心配&心配の今年の春。
そんななか、先日新たに配食をスタートした豊中のお客様H様に
訪問してきました。
(その日もあいにくの雨模様のなか)
5月初旬に担当のケアマネジャーさんから
「いまは、施設の入所しているのだけど20日すぎには退所
しないといけない方がいて、施設でカロリー制限しているのに
血糖が200ぐらいあって、Drからも特に指導がない状態なんです。
これってお食事でなんとかできますか?
自宅に帰られてからも療養できますかね?」と相談が
「できますよ。大丈夫です。
血糖が常時200でほっておくDrもどうかと思いますが
本来は悪くても150以下に抑えないとダメでしょう。食事で十分管理可能です」
と、即答し
「じゃあ、お願いします」ということで新しくサポートさせていただける方をゲット。
ご本人は入所中でしたので先にご自宅でケアマネジャーさんとご主人と3人
(正確には寺田さんも同行したので4人)で自宅復帰後の食事について相談
させていただきました。
いままではご主人がスーパーなどで買い物をされてきて惣菜主体のお食事だったそうで
自宅に戻られた食事をすごく心配されていました。
血糖も持続的に高いことから昼夕毎日のお届けになり朝食はご自宅でちゃんと食べていただくことに。
スタート後、「お食事はしっかり食べていただけているようですよ」と配送員からの
報告を受けて一安心していたのですが、訪問時はご本人様とお話しできなかったので
先日ご挨拶に伺いました。
「朝食にも野菜は食べてくださいね」とお伝えしていたところ
「娘がサラダを作ってきてくれるので、それを食べている」とのこと。
入所中はちょこちょこ食べていたと聞いた間食も、いまのところストップ中です。
ただ、就寝前の血糖は150ぐらいですが朝食前が250ぐらいあって高く
インスリンの量も往診にこられることになったDrが増やされたのですが
なかなかすぐには安定されていない様子。
(安定への道は一歩一歩ですね、やはり)
大丈夫です!といった手前しっかりとフォローしてよくなる結果を
本人にもケアマネジャーにも実感してもらえるようお手伝いしていきたいと思います。
はーと&はあと 管理栄養士 島田天心
今年一年の北摂の様子は
『もっと☆めでぃ北摂ブログ』でもご紹介しています。ご覧ください。